テーマ1
病気だと思わず練習に出られない自分を責めた日々 ――治療目標の認識
起きていられないほどだるい、力が入らないといった、漠然とした体調の悪さを自覚するようになったのは大学3年生のときです。チアリーディング部の海外遠征からの帰国後、空港で倒れて救急搬送されたこともありました。
ただ、もともと身体が弱く日常的に不調を感じることが多かったので、重症筋無力症(MG)と診断されるまで病気だとは思っていませんでした。だからこそ、皆は部活もアルバイトもこなしているのに、体調が悪くて大学に行けずチアの練習にも出られない自分を、なんて弱いんだろうと責めることが多かったですね。MGと医師から病名を告げられたときには、こんなに具合が悪かったのは病気のせいだったんだと分かり、むしろほっとしました。
でも、MG治療が始まってもなかなか体調はよくならず、入院期間は3カ月、そして半年と延びていきました。入院が長引くと復学のタイミングも見えなくなり不安はどんどん膨らんでいきましたが、その不安な気持ちから目を背け、寝たきりの状態のまま、「絶対に復学する」とひたすら言い続けていました。
転機になったのは、MGクリーゼ*1で初めて人工呼吸器につながれたときです。呼吸が苦しくなってあっという間に意識を失い、気付いたら集中治療室(ICU)にいました。こんなにもあっけなく死んでしまうかもしれないことに衝撃を受け、自分のマインドが変わったように思います。
自分の中にある不安を受け入れ、寝たきりの今の状態では復学も社会に出て働くことも難しいとしっかり認識したうえで、これからどうするかを考えました。はっきりしたのは、復学や就職を実現するために治療をしたい、それが私のMG治療の目標なんだということでした。

-
*1 MGクリーゼ…急激な症状悪化により呼吸筋力が低下し呼吸困難を起こした状態
テーマ2
病気以外の“アイデンティティ”を求めて復学・就職

1年近くの入院を2回繰り返した後、思い切って病院を変えました。治療を続けるうちに病状が落ち着いて大学に戻ることができ、そこから就職活動をして2年遅れで社会人になりました。
そこに至るまでには、なぜ私が周囲に復学や就職にここまでこだわるのか理解してもらえず、孤独を感じたこともありました。でも、私のアイデンティティが「MGの佐藤さん」だけになってしまうのは、避けたいと思いました。MGではあるけれども、私は「学生の佐藤」や「A社の佐藤」でもある。そのために、復学や就職は譲れなかったのです。
また、病気を言い訳にしたくはない、という私個人の思いもありました。MGのことは一部の友だちにしか打ち明けていなかったので、入院中に就職活動の相談メールを友だちから受けることもよくありました。そんなとき、周りの人の時間は進んでいて、自分はもう取り残されているんだなと実感しました。
私には大学入学時から目指していた仕事があり、そのための準備も重ねていました。だからこそ、内定が決まっていく友だちを見て内心悔しさを感じることもありました。同時に、この病気になったからこそ得られた視点を、社会に出て何かの形で還元したいという強い思いも抱くようになっていました。
そこで、職種は違っても同じ業界に入り、フルタイムで働きたいと考えました。主治医に就労環境・業務内容等の制限や配慮に関するアドバイスをもらいながら就職活動を行い、有難いことにご縁のあった会社で勤務する事ができています。入社後も、主治医が定期的に会社の産業医に意見書を書いてくれ、投薬等の治療面以外のサポートもあって、『働く』という夢を叶えることができています。
テーマ3
今の生活とやりがい
今の私は働くために治療し、土日はほぼ自宅で過ごして疲れをためないようにするなど、仕事のために生活全般をセーブしています。電車通勤が難しいため、自宅は会社から徒歩圏内です。周りに人がいて小刻みに揺れる電車内で10分も立ち続けていると、疲れて症状に現れてしまうのです。通院や外出時にはタクシーも利用しています。
大変なのは症状の日内変動*2です。昼過ぎには左の眼瞼下垂*3が始まり、パソコン画面がぶれて見えるので、ひどいときは眼帯をつけ凌いでいます。夕方になるとろれつが回らなくなり、会議などで話が聞き取りにくいと言われることもあります。
ただ、入社して3年経ちますが、症状の増悪はなく、同僚にも良い意味で私の病気のことを忘れてもらえているように思います。その半面、外見からは分からない障害なので、「なぜ午前中にできたことが午後にはできないの?」などと質問されることもあります。そうしたときは、私は気を遣われ過ぎないように、知っていただきたい最小限のことだけお話しするようにしています。
働くことは今の私にとって1番のモチベーションです。ただベッドで天井だけを見て過ごしていた入院生活と社会では、時間のスピードが全く違うことを感じています。業務を任され、責任を負って仕事に向き合っていると1日はあっという間です。そして、こうした社会のサイクルの中に自分がいることがとても嬉しいのです。
また、業務を担当すると、「A社の佐藤」「B業務担当の佐藤」と、アイデンティティが増えていきます。病気の自分とは違った自分がいる充実感がありますね。そして、働いたお金で、おしゃれなど好きなことをするのも明日への活力になっています。

-
*2 ⽇内変動…MG症状が1⽇の中で変動すること。筋⾁をよく動かした後の⼣⽅以降は症状が重くなることがある。
- *3 眼瞼下垂…まぶたがさがってくる症状。MGの症状の1つ。
テーマ4
治療の“主権”は私 主治医とは同じ目線で話したい ――SDM (Shared Decision Making:共同意思決定)
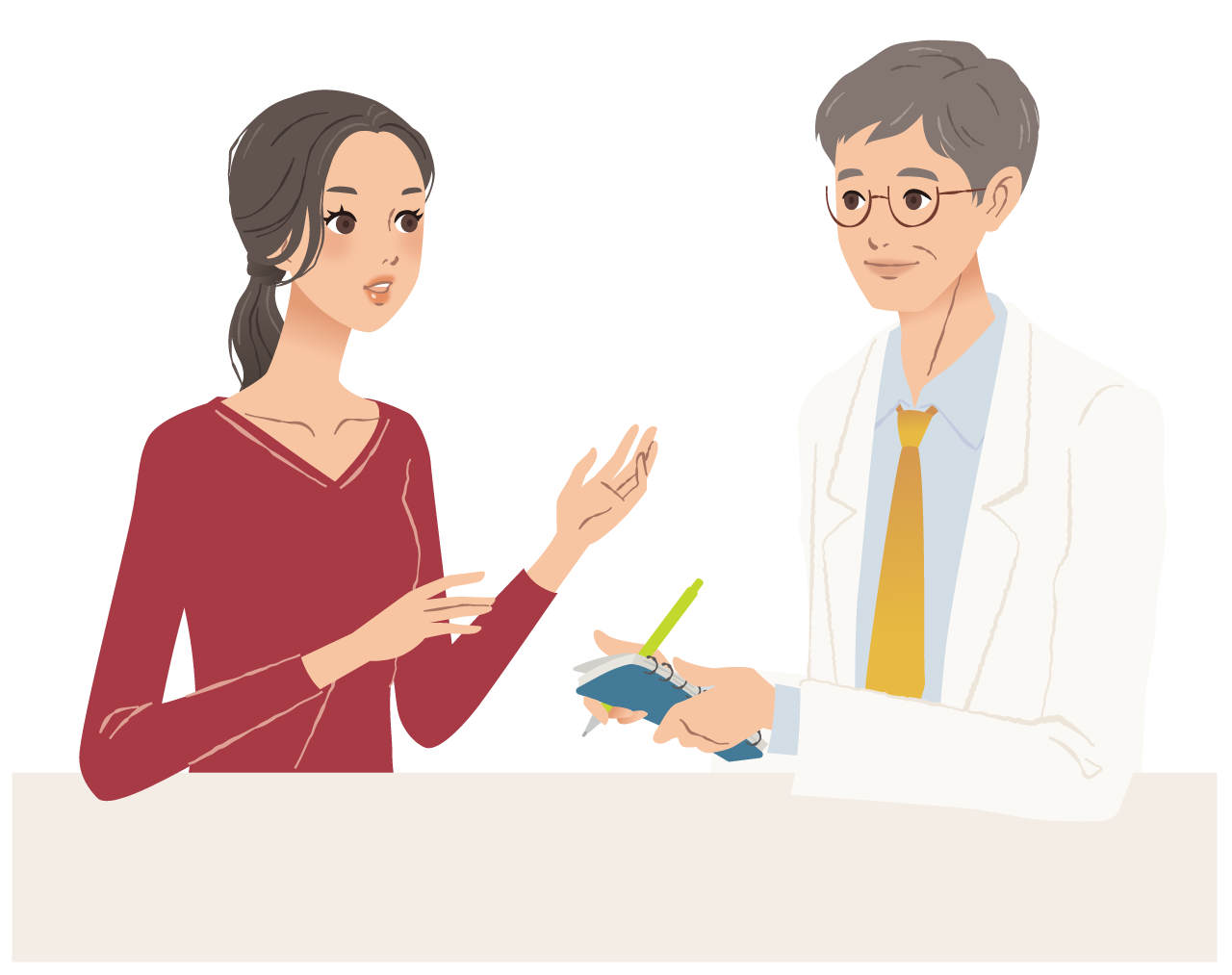
私が主治医の先生に望んでいたのは、「大学に復学して就職したい」という私の目標を理解し、治療方針を立ててくださることです。そのため、病院を移ったばかりのときに、先生に話をする時間をつくっていただきました。
治療する目的をお伝えしたうえで、これまでの治療と経過を説明し、自分の生活や目標などを見直す必要があるのかうかがいました。治療がうまくいかないとき、私は自分に何か悪いところがあるのではと思いがちです。そのため、専門家としての意見をお聞きするとともに、先生のスタンスや人柄も知りたいと考えました。先生が私の目標を否定せず、治療の選択肢も一つではない、他にも治療法がある、と示してくださったことで、この先生と一緒に復学や就職を目指したいと思いました。
現在、日常の病状管理は、病院から渡されたツールにより、症状をスコア化して重症度を毎日評価するのとあわせて、症状悪化のリスクになる仕事量や日々の出来事などをメモするようにしています。受診日には これらの記録を一緒にして主治医に見ていただいています。
MGで私が1番怖いのはベースとなる病状の悪化です。日々の症状のスコアとメモを照らし合わせれば、症状の悪化が仕事の疲れなどによるものか、ベースの病状の悪化によるものか把握する手がかりになります。ただし、そうした判断を全て主治医任せにするのではなく、自分でも状態を分析したうえで、先生の考えをうかがうようにしています。
私は医師と同じ目線で話したいと考えています。自分の人生のことなので、治療の“主権”を自分で持ち続けたいと思います。
テーマ5
将来の目標は独立して自分1人で生活すること
MGを発症してから、母が上京して家事をしてくれています。私が週5日働けているのは母のおかげです。
最近では、母もひと月の3分の1程度は実家に戻れるようになり、その間は就職を機に同居するようになった妹と一緒に家事をしています。例えば、物を持つのが辛いときには、皿洗いを途中で代わってもらい洗濯物を畳むなど、「私にできることをやるのでできないことはお願いね」と、いい意味で分担できています。
妹は私の経過を見ているので、2人で外出するときも「この駅はかなり歩くから別のルートにしよう」などと、私に無理のない動線を“当たり前のこと”として考えてくれます。そうしたことがとてもありがたいなと思っています。
でも、家族には私の病気にとらわれ過ぎないでほしいとも思っています。私に病気があるのは当たり前のこととして特別扱いせず、旅行に行くなど1日24時間を自分のやりたいことに使うなど、自分自身のことを優先してもらいたいのです。
私も今後のライフプランを考える時期に来ています。将来の目標は、完全に独立して1人で生活することです。病気だから家族が支えなければいけないのではなく、私が自分で生活できる体制がつくれたら、私にも家族にとっても最善だと思います。それには段階が必要なので、まずは親の力を借りず、妹と2人で生活する期間を月の3分の1から増やしていき、自分の力で生活する練習をしたいと思っています。
私の選択は一例です。病気も家族の形も、治療方針も十人十色です。皆さんがそれぞれ自分に合い、納得できる治療や生活の形を見つけていくことが1番だと思います。

紹介した症例は臨床症例の一部を紹介したもので、全ての症例が同様な経過、結果を示すわけではありません。





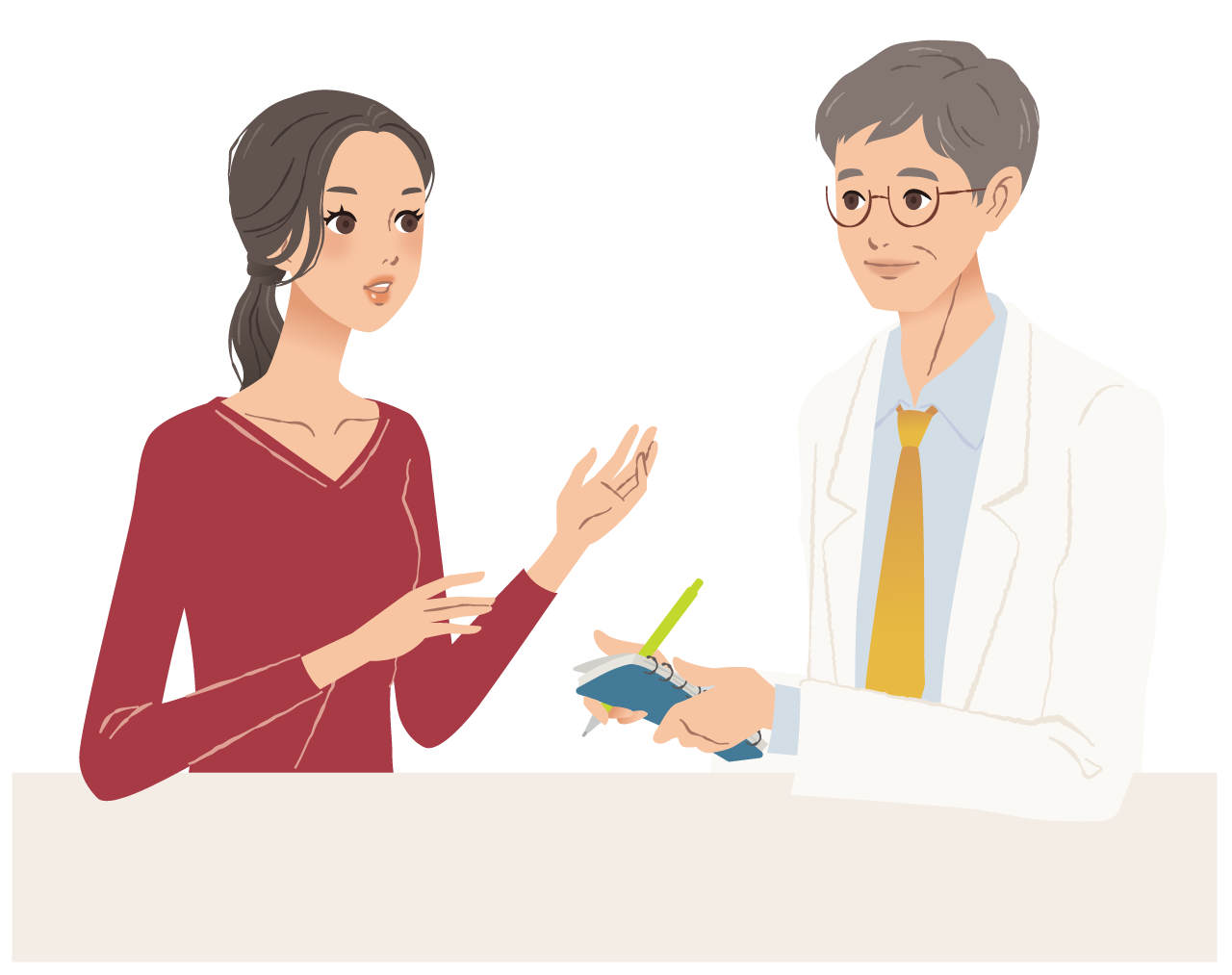



監修︓ 脳神経内科 千葉 川口 直樹 先生
重症筋無力症(以下MG)は瞼が下がったり二重に見えたりすることがあります。手足の筋力が保持できなかったり、咀嚼・嚥下(食べ物を噛むことや飲み込むこと)や呼吸がうまくできなくなることもあります。手記の女性のように日常生活の不自由ばかりでなく社会生活にも影響しかねない病気です。
MGは病原性自己抗体(抗アセチルコリン受容体抗体あるいは抗マスク抗体)が原因で発症する自己免疫の病気であり、基本的には免疫を抑える治療が行われます。ステロイドが主役ではありますが、多様な副作用が懸念されます。このためほかの治療も早期から積極的に併用し、少量のステロイド使用でなるべく早く症状を改善させることを目指すようになっています。抗アセチルコリン受容体抗体が病原性を発揮するときに活性化する蛋白である補体をターゲットとする治療も行われることもあります。これら治療の進歩によりMGで亡くなる方は現在殆どありません。
しかしMGは若い方・働き盛り・子供に多く発症しますし、高齢者の患者さんも増えてきています。MG症状や治療の負担のために年齢相応の社会生活を営むことができないのでは治療の結果としては満足できるものではありません。治療効果ばかりでなく、その副作用や心身への負担を最低限に抑えることが望まれます。そのために主治医・医療スタッフとの信頼関係のもとで適切な治療を早期から受けることにより患者さんの悩みや苦しみが軽減することを願っています。